제18회 지능형자율시스템 국제컨퍼런스 5일 개막식 개최

▲5日朝、水原コンベンションセンター3階で開かれた第18回知能型自律システム国際カンファレンス(IAS18-2023)開幕式の様子第18回知能型自律システム国際カンファレンス(The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems·IAS18-2023)が知能型自律システム(IAS)協会主催、制御ロボットシステム学会主管で4日から水原コンベンションセンター3階で開幕した。▲会場の案内板の様子=5日午前に開かれた開幕式には、李淳杰(イ·スンゴル)組織委員長(慶煕大学教授)、李錫漢(イ·ソクハン)名誉組織委員長(成均館大学教授)、安鎮雄(アン·ジンウン)プログラム委員長(DGIST教授)、鄭洛栄(チョン·ナクヨン)アジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)、金ジュヒョン米州地域プログラム委員長など国内外から150人余りが参加した。▲イ·スンゴル組織委員長が5日、京畿道水原コンベンションセンターで開かれた「第18回知能型自律システム国際カンファレンス」開幕式で歓迎の挨拶をしている。イ·スンゴル組織委員長は歓迎の辞を通じて「11年前の2012年、第12回IASカンファレンスが済州道で開かれて以来、韓国で2回目に開かれる今回のカンファレンスをユネスコ世界遺産である華城がある歴史的場所水原で開催することになった」として「これまで新型コロナウイルス感染症によって2021年シンガポール、2022年クロアチアザグラブでこの2年間オンラインとハイブリッドで開かれたが、完全な対面方式で今回のカンファレンスを開催することになり嬉しい」と話した。 イ委員長は「今回のカンファレンスには4つの基調講演およびキーノートセッション、15の発表セッション、8つの特別セッション、1つのインタラクティブセッションとインダストリアルセッションが用意されており、計136編のポスターおよび発表論文が受け付けられた」と明らかにし「文化遺産がある水原で準備したカンファレンスプログラムを楽しめることを願う」と話した。▲チョン·ナクヨンアジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)が祝辞を述べている。▲来年度IAS19-2024組織委員長であるイタリアのジェノア大学プルビオ·マストロジオバンニ教授が祝辞を述べている。歓迎の挨拶に続き、アジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)と来年度IAS19-2024組織委員長であるイタリアジェノア大学フルビオ·マストロジオバンニ教授が祝辞を述べた。▲フラナリー講演が開かれた水原コンベンションセンター行事会場の様子で、成均館大学校イ·ソクハン教授が「Deep 3D Vision for Intelligent Autonomous Systems(知能型自律システムのための深層3Dビジョン)」を主題に最初のプレナリー講演に出た。▲成均館(ソンギュングァン)大学の李ソクハン教授が最初のプレナリー講演を行っている。イ教授は「人間と大部分の動物と同様に、3Dビジョンは自律システムとエージェントが自律的な探索、操作および相互作用を基盤に実際世界の活動と作業を遂行するのに必須だ。 特に、自律エージェントが空間-時間的脈絡で周辺3D場面と作業空間を理解、モデリングおよび測定できる能力は人間と類似した自律性を達成するための根本的な役割を果たす。「追加的な次元によって発生する大規模6D幾何学的変化により3D処理の複雑性が増加し、3D幾何学的特徴を利用した2Dビジョンの拡張に基づいた伝統的な工学アプローチは効率性と正確性のバランスを取ることが難しく制限された成功だけを提供することができた」と話した。 それと共にイ教授は「最近のエンドツーエンドディープラーニング方式を活用した3D場面および作業空間モデリング、オブジェクト6D姿勢推定、探知、パンオプティックセグメンテーション(Panoptic Segmentation)および追跡に対する最近の進展は自律システムとエージェントがリアルタイムで3D場面と作業空間を理解、モデリングおよび測定するのにおいて人間と類似した性能を達成できる可能性を開いた。」と強調した。イ教授は講演を通じて、3Dビジョンにおけるディープラーニングアプローチの発展と3Dシーンおよび作業空間モデリングと6Dオブジェクト姿勢推定に対するエンドツーエンドディープラーニングアプローチについて説明し、成均館大学知能システム研究所が開発した3Dビジョンに対するエンドツーエンドディープラーニングアプローチを紹介しながら、部分から全体ポイントクラウド再構成およびオブジェクトおよびカテゴリレベルでの6D姿勢推定へのアプローチを深いオブジェクト検出とファンタスティックセグメンテーションと統合してリアルタイム3Dシーンモデリングに適用する方法を説明した。 続いて、開発されたディープ3Dビジョンがスマート製造、自律探索および人間-ロボット相互作用にどのように適用されたかについて発表し、知能型自律システムのためのディープ3Dビジョンの未来方向について討論した。▲基調講演が行われた水原コンベンションセンターの会場の様子=午後には、米国パデュー大学リチャード·M·ボイレス教授が「The Irony of Autonomy: The Increasing Involvement of Humans in Assistive Monitoring and Active Interaction(自律性のアイロニー:補助モニタリングおよび能動的相互作用への人間の参加増加)」をテーマに基調講演を行った。▲米パデュー大学のリチャード·M·ボイレス教授が基調講演を行っている。ボイレス教授は「この35年間、自律システム研究で皮肉な転換はより多くの人間をループ(Loop)に含ませることだった。 アリストテレス時代から人間は労働の束縛から逃れるために自分と似た形の自動機械を作るアイデアに魅了されてきた。 したがって、60年前頃の最初の工場ロボットの目標は、人間の介入なしに厳格な時間割に従って作動する「光のない工場(lights-out factories)」を作ることだった。 しかし、従順な自動機械を作ろうという願いと共に、私たち自身の知能的な機械の反乱に対する恐怖も長い歴史を持っている。 人間は人間の感情の根本的な予測ができないことを機械的子孫の論理的な苦労と混同しようとしているようだ。 そのため、現在自律性研究の頂点は訓練を受けていない人間受恵者と非構造的(unstructured)で混沌とした環境でスムーズに協力する機械に移動しているのはそれほど驚くべきことではないかもしれない」と話した。ボイレス教授は講演で「独立した機械からますます技術的無知がより大きな人間と相互作用する機械への自律システム研究の進化を説明しながら、ロボット組立から自動運転車両、非常対応およびロボット手術に至るまで、私たちは次第に最新技術の限界を越えて構造化が少ない状況でますます高い知能を持つ機械と人間の相互作用に挑戦している」と述べた。 彼は「この領域で非常対応研究コミュニティは人間の協力制御が必須な難しいシナリオで非常に構造的でない環境を攻撃するために決然とした努力を傾けた」とし「米国で発生した9/11テロによるワールドトレードセンターの災難状況でロボットが実際に使われた最初の事例であり、ほとんど自律性が許されなかった」と話した。 彼は「この当時、被害者探索があまりにも難しくリアルタイムで訪れた被害者の約60%はリアルタイムではなくビデオ映像の事後分析で発見された」として「解体された環境での探索は事前基盤モデル情報が大部分使用できず、ホコリと残骸によって認識が不安定になるため難しい問題」と話した。 ボイレス教授は「初期の試みではテレオペレーションが人間の生命をかけることができる唯一の解決策であり、以後DARPAロボットチャレンジは全世界の研究者を集めて機械と人間の増強のための自律性の高い水準とオフラインおよびオンラインシミュレーションを統合することに進化した。「この進化は戦場ロボット手術の非構造化された世界につながり仮想化された現実がテレオペレーションを完全な自律性と融合し危機状況で機械が人間専門家から学習し完全な自律性を支援できる方式で進行している」と説明した。▲5日午前に開かれたオートノマスナビゲーションセッションで講演する慶応大学講演者▲ロボットと人工知能のためのデジタルツイニングセッションの様子▲デジタルツインとハプティックインターフェースセッションの様子▲物体探知セッションの様子以外にも、5日には午前中に自律ナビゲーション、ロボットと人工知能のためのデジタルツイニング、デジタルツインとハプティックインターフェース、オブジェクト探知、午後にはポーズ推定、上肢リハビリロボット、挑戦的な環境でのロボット技術デジタルツインのためのSLAM、自律エージェントでのスマートセンサーなどに対する多様なセッションが行われた。▲アン·ジンウンプログラム委員長がフラナリーセッション座長を務め、講演者を紹介している。行事3日目の6日には日本名古屋大学和也武田教授が「AI technology for mitigating the risk of AI(人工知能)危険を緩和するAI技術)」を主題にした基調講演とワークショップ、チュートリアルが開かれ、午後にはソウル大学融合科学技術大学院研究室ツアー、インダストリアルセッションと授賞式、そしてカンファレンス晩餐が進行される。最終日の7日午前には米国ミシガン大学ガボール·オーローズ教授が「Connected and automated vehicles:improving safety and efficiency across the scales(コネクテッドおよび自律車両:スケールを越えて安全および効率性改善)」を主題に基調講演と多様なセッションが開かれ、午後には閉幕式が開かれ、今年「第18回知能型自律システム国際カンファレンス(The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems·IAS18-2023)」を幕を閉じる。▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲慶熙大学校IRMSラップブースの様子▲ファルコンライダー 販売業者のイノビュージョンブースの様子▲ファルコンライダー▲ビーアンドソフトブースの様子▲大邱モバイルマニピュレーター規制自由特別ゾーンブースの様子▲ルミソルブースの様子▲エナテックスブースの様子▲ウィゴロボティクスブースの姿▲カルマンテックブースの様子▲ファンクションベイブースの姿チョ·ギュナム専門記者 [email protected] <著作権者ロボット新聞社無断転載及び再配布禁止>

▲5日朝、水原コンベンションセンター3階で開かれた第18回知能型自律システム国際カンファレンス(IAS18-2023)開幕式の様子第18回知能型自律システム国際カンファレンス(The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems·IAS18-2023)が知能型自律システム(IAS)協会主催、制御ロボットシステム学会主管で4日から水原コンベンションセンター3階で開幕した。▲会場の案内板の様子=5日午前に開かれた開幕式には、李淳杰(イ·スンゴル)組織委員長(慶煕大学教授)、李錫漢(イ·ソクハン)名誉組織委員長(成均館大学教授)、安鎮雄(アン·ジンウン)プログラム委員長(DGIST教授)、鄭洛栄(チョン·ナクヨン)アジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)、金ジュヒョン米州地域プログラム委員長など国内外から150人余りが参加した。▲イ·スンゴル組織委員長が5日、京畿道水原コンベンションセンターで開かれた「第18回知能型自律システム国際カンファレンス」開幕式で歓迎の挨拶をしている。イ·スンゴル組織委員長は歓迎の辞を通じて「11年前の2012年、第12回IASカンファレンスが済州道で開かれて以来、韓国で2回目に開かれる今回のカンファレンスをユネスコ世界遺産である華城がある歴史的場所水原で開催することになった」として「これまで新型コロナウイルス感染症によって2021年シンガポール、2022年クロアチアザグラブでこの2年間オンラインとハイブリッドで開かれたが、完全な対面方式で今回のカンファレンスを開催することになり嬉しい」と話した。 イ委員長は「今回のカンファレンスには4つの基調講演およびキーノートセッション、15の発表セッション、8つの特別セッション、1つのインタラクティブセッションとインダストリアルセッションが用意されており、計136編のポスターおよび発表論文が受け付けられた」と明らかにし「文化遺産がある水原で準備したカンファレンスプログラムを楽しめることを願う」と話した。▲チョン·ナクヨンアジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)が祝辞を述べている。▲来年度IAS19-2024組織委員長であるイタリアのジェノア大学プルビオ·マストロジオバンニ教授が祝辞を述べている。歓迎の挨拶に続き、アジア/オセアニア地域プログラム委員長(日本JAIST教授)と来年度IAS19-2024組織委員長であるイタリアジェノア大学フルビオ·マストロジオバンニ教授が祝辞を述べた。▲フラナリー講演が開かれた水原コンベンションセンター行事会場の様子で、成均館大学校イ·ソクハン教授が「Deep 3D Vision for Intelligent Autonomous Systems(知能型自律システムのための深層3Dビジョン)」を主題に最初のプレナリー講演に出た。▲成均館(ソンギュングァン)大学の李ソクハン教授が最初のプレナリー講演を行っている。イ教授は「人間と大部分の動物と同様に、3Dビジョンは自律システムとエージェントが自律的な探索、操作および相互作用を基盤に実際世界の活動と作業を遂行するのに必須だ。 特に、自律エージェントが空間-時間的脈絡で周辺3D場面と作業空間を理解、モデリングおよび測定できる能力は人間と類似した自律性を達成するための根本的な役割を果たす。「追加的な次元によって発生する大規模6D幾何学的変化により3D処理の複雑性が増加し、3D幾何学的特徴を利用した2Dビジョンの拡張に基づいた伝統的な工学アプローチは効率性と正確性のバランスを取ることが難しく制限された成功だけを提供することができた」と話した。 それと共にイ教授は「最近のエンドツーエンドディープラーニング方式を活用した3D場面および作業空間モデリング、オブジェクト6D姿勢推定、探知、パンオプティックセグメンテーション(Panoptic Segmentation)および追跡に対する最近の進展は自律システムとエージェントがリアルタイムで3D場面と作業空間を理解、モデリングおよび測定するのにおいて人間と類似した性能を達成できる可能性を開いた。」と強調した。イ教授は講演を通じて、3Dビジョンにおけるディープラーニングアプローチの発展と3Dシーンおよび作業空間モデリングと6Dオブジェクト姿勢推定に対するエンドツーエンドディープラーニングアプローチについて説明し、成均館大学知能システム研究所が開発した3Dビジョンに対するエンドツーエンドディープラーニングアプローチを紹介しながら、部分から全体ポイントクラウド再構成およびオブジェクトおよびカテゴリレベルでの6D姿勢推定へのアプローチを深いオブジェクト検出とファンタスティックセグメンテーションと統合してリアルタイム3Dシーンモデリングに適用する方法を説明した。 続いて、開発されたディープ3Dビジョンがスマート製造、自律探索および人間-ロボット相互作用にどのように適用されたかについて発表し、知能型自律システムのためのディープ3Dビジョンの未来方向について討論した。▲基調講演が行われた水原コンベンションセンターの会場の様子=午後には、米国パデュー大学リチャード·M·ボイレス教授が「The Irony of Autonomy: The Increasing Involvement of Humans in Assistive Monitoring and Active Interaction(自律性のアイロニー:補助モニタリングおよび能動的相互作用への人間の参加増加)」をテーマに基調講演を行った。▲米パデュー大学のリチャード·M·ボイレス教授が基調講演を行っている。ボイレス教授は「この35年間、自律システム研究で皮肉な転換はより多くの人間をループ(Loop)に含ませることだった。 アリストテレス時代から人間は労働の束縛から逃れるために自分と似た形の自動機械を作るアイデアに魅了されてきた。 したがって、60年前頃の最初の工場ロボットの目標は、人間の介入なしに厳格な時間割に従って作動する「光のない工場(lights-out factories)」を作ることだった。 しかし、従順な自動機械を作ろうという願いと共に、私たち自身の知能的な機械の反乱に対する恐怖も長い歴史を持っている。 人間は人間の感情の根本的な予測ができないことを機械的子孫の論理的な苦労と混同しようとしているようだ。 そのため、現在自律性研究の頂点は訓練を受けていない人間受恵者と非構造的(unstructured)で混沌とした環境でスムーズに協力する機械に移動しているのはそれほど驚くべきことではないかもしれない」と話した。ボイレス教授は講演で「独立した機械からますます技術的無知がより大きな人間と相互作用する機械への自律システム研究の進化を説明しながら、ロボット組立から自動運転車両、非常対応およびロボット手術に至るまで、私たちは次第に最新技術の限界を越えて構造化が少ない状況でますます高い知能を持つ機械と人間の相互作用に挑戦している」と述べた。 彼は「この領域で非常対応研究コミュニティは人間の協力制御が必須な難しいシナリオで非常に構造的でない環境を攻撃するために決然とした努力を傾けた」とし「米国で発生した9/11テロによるワールドトレードセンターの災難状況でロボットが実際に使われた最初の事例であり、ほとんど自律性が許されなかった」と話した。 彼は「この当時、被害者探索があまりにも難しくリアルタイムで訪れた被害者の約60%はリアルタイムではなくビデオ映像の事後分析で発見された」として「解体された環境での探索は事前基盤モデル情報が大部分使用できず、ホコリと残骸によって認識が不安定になるため難しい問題」と話した。 ボイレス教授は「初期の試みではテレオペレーションが人間の生命をかけることができる唯一の解決策であり、以後DARPAロボットチャレンジは全世界の研究者を集めて機械と人間の増強のための自律性の高い水準とオフラインおよびオンラインシミュレーションを統合することに進化した。「この進化は戦場ロボット手術の非構造化された世界につながり仮想化された現実がテレオペレーションを完全な自律性と融合し危機状況で機械が人間専門家から学習し完全な自律性を支援できる方式で進行している」と説明した。▲5日午前に開かれたオートノマスナビゲーションセッションで講演する慶応大学講演者▲ロボットと人工知能のためのデジタルツイニングセッションの様子▲デジタルツインとハプティックインターフェースセッションの様子▲物体探知セッションの様子以外にも、5日には午前中に自律ナビゲーション、ロボットと人工知能のためのデジタルツイニング、デジタルツインとハプティックインターフェース、オブジェクト探知、午後にはポーズ推定、上肢リハビリロボット、挑戦的な環境でのロボット技術デジタルツインのためのSLAM、自律エージェントでのスマートセンサーなどに対する多様なセッションが行われた。▲アン·ジンウンプログラム委員長がフラナリーセッション座長を務め、講演者を紹介している。行事3日目の6日には日本名古屋大学和也武田教授が「AI technology for mitigating the risk of AI(人工知能)危険を緩和するAI技術)」を主題にした基調講演とワークショップ、チュートリアルが開かれ、午後にはソウル大学融合科学技術大学院研究室ツアー、インダストリアルセッションと授賞式、そしてカンファレンス晩餐が進行される。最終日の7日午前には米国ミシガン大学ガボール·オーローズ教授が「Connected and automated vehicles:improving safety and efficiency across the scales(コネクテッドおよび自律車両:スケールを越えて安全および効率性改善)」を主題に基調講演と多様なセッションが開かれ、午後には閉幕式が開かれ、今年「第18回知能型自律システム国際カンファレンス(The 18th International Conference on Intelligent Autonomous Systems·IAS18-2023)」を幕を閉じる。▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲韓国ロボット産業振興院展示ブースの様子▲慶熙大学校IRMSラップブースの様子▲ファルコンライダー 販売業者のイノビュージョンブースの様子▲ファルコンライダー▲ビーアンドソフトブースの様子▲大邱モバイルマニピュレーター規制自由特別ゾーンブースの様子▲ルミソルブースの様子▲エナテックスブースの様子▲ウィゴロボティクスブースの姿▲カルマンテックブースの様子▲ファンクションベイブースの姿チョ·ギュナム専門記者 [email protected] <著作権者ロボット新聞社無断転載及び再配布禁止>

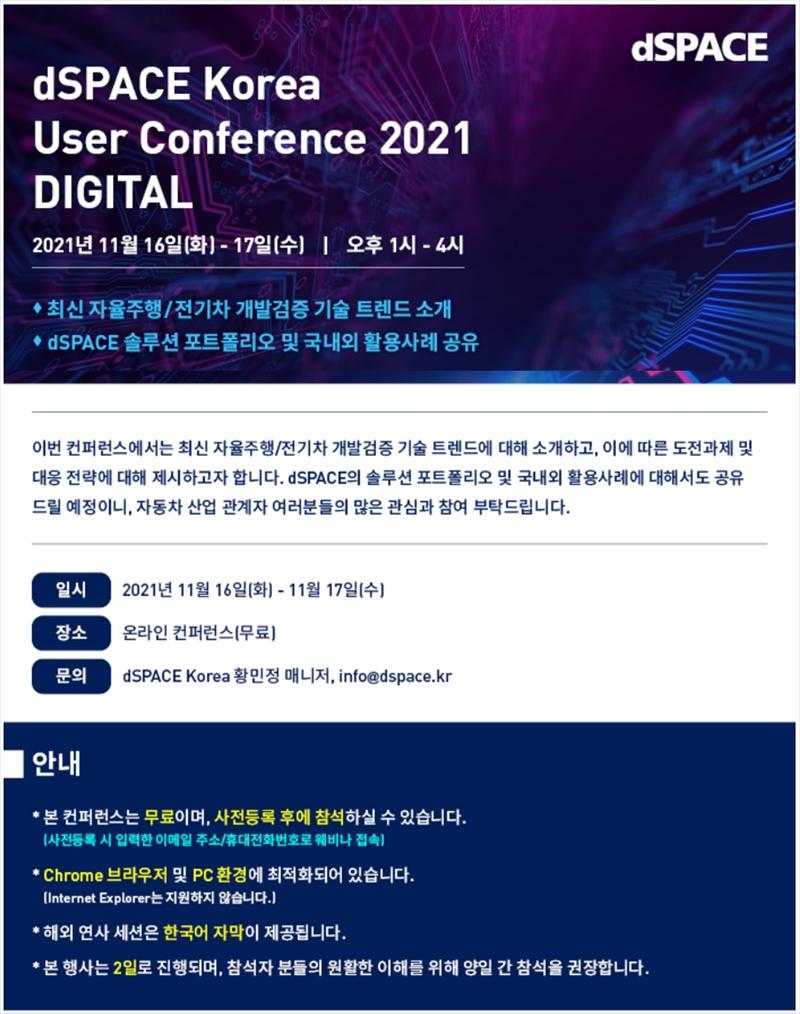









![[만화 #2-2] 이말년 수필_웹툰 리뷰_침착한 수작 [만화 #2-2] 이말년 수필_웹툰 리뷰_침착한 수작](https://rain.proup.kr/wp-content/plugins/contextual-related-posts/default.png)